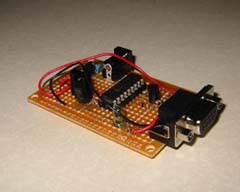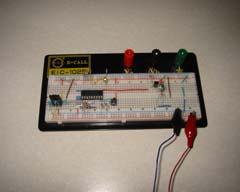NIKON D70用タイマーリモコン制作
EOSにも対応!!
by船長っ
|
○事の始まり キャノンから発売された「EOS Kiss D」につづいて04年に発売されたデジタル一眼レフ「Nikon D70」。船長っはこれを待っていました。 デジタル一眼が出始めた頃からとても興味はあったのですが、当時はウン十万と言う途方もない値段で、中古のFG−20を高校時代から使っている船長っには高嶺の花でした。そこにキャノンから10万円台で買えるデジタル一眼レフが発売になり、「これは近々Nikonからも出るな」と待っていたんです。何でNikonにこだわるのかと言うと、既にNikonのレンズを何本か持っていたから。ただそれだけです。 で、買ってみたD70ですが、シャッターボタンにレリーズを取り付けることが出来ないんですね。これは、天体写真を撮る際は大きなハンデになります。シャッターのON/OFF時にブレますからね。で、どうするのかというと赤外線リモコンを使って操作するんです。これを使うと、以前のFG−20よりも遥かに操作性が良いんです。船長っ的にはこれでもかなり満足していたんです。 D70に関しては掲示板やメールでいろんな情報(天体写真に関するもの)をいただいていたんですが、その中に「タイマーリモコンが発売された」と言うものがありました。これは便利なものが!!と思ったのですが、問題は値段だったんですね。高かったんです。材料や手間など考えると妥当な線なんですが・・・。ちょっと手が出ませんでした。 |

D70はNikonから出た廉価版(?)のデジタル一眼レフ。現在はIRカットフィルターを光映舎のものに交換してあります。散光星雲の写りは格段に良くなりました。 |
| ○調べてみる
ちょうど、PICマイコンにハマっていて、これまたちょうど、デジタル温度計の制作に行き詰まっていたところでした。何か他に取り組める題材はないものかと思っていたんです。「赤外線リモコン」、作るのもおもしろいかもと飛びついてしまったのです。 もともと赤外線リモコンについて全くと言っていいほど知識が無かった船長っは「ふっ、結局チカチカと赤外線LEDが点滅するだけだろうよ!」と軽くみていたんですね。 早速、赤外線を「見る」ために、エビライブに使っているデジカメでリモコンの作動状況を見てみることにしました。 ・・・・馬鹿ですよねぇ、本当に船長っはアホです。「見れば点滅の状況が解る」と思っていたんです。解るわけないです。点滅は速すぎて見た目は「ピカァ」と一瞬光るだけでした。当たり前です。 で、これはイカンと調べてみたら、赤外線リモコンについてはこんなページやこんなページが出てきました。(直リンクごめんなさい) 大まかに言うと赤外線リモコンのフォーマットは家電製品フォーマットとNECフォーマットと独自フォーマットがあり、搬送波(船長っは全く理解していません・・・・)はだいたい38KHzなんだそうです。そして、ピカッと光った後に続く消灯している時間の長さで0と1の信号を区別するんだそうです。 ここまで調べても船長っの頭の中では「点滅を繰り返すだけ」と言う理解のみが渦を巻いていたのでした。 |

これが純正のリモコン。2000円程度します。 |